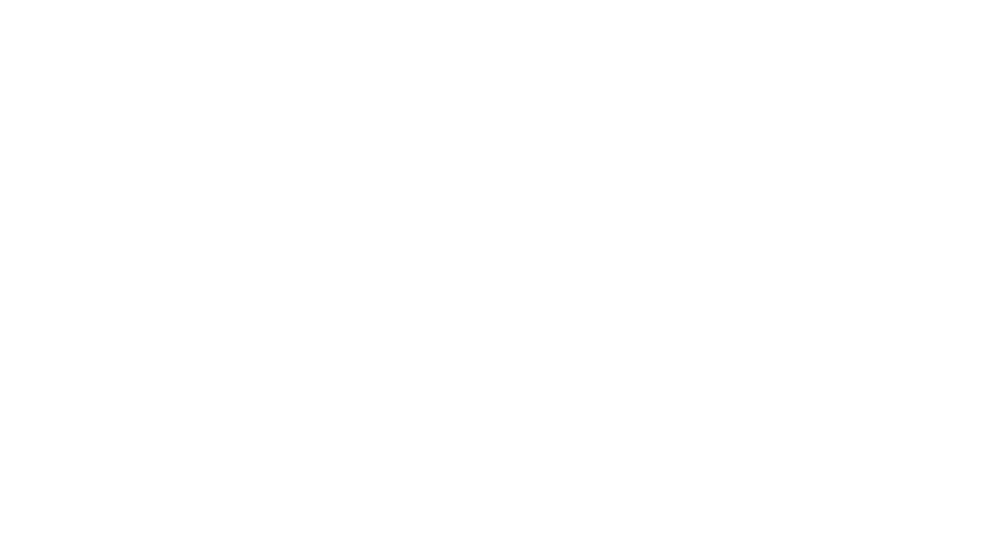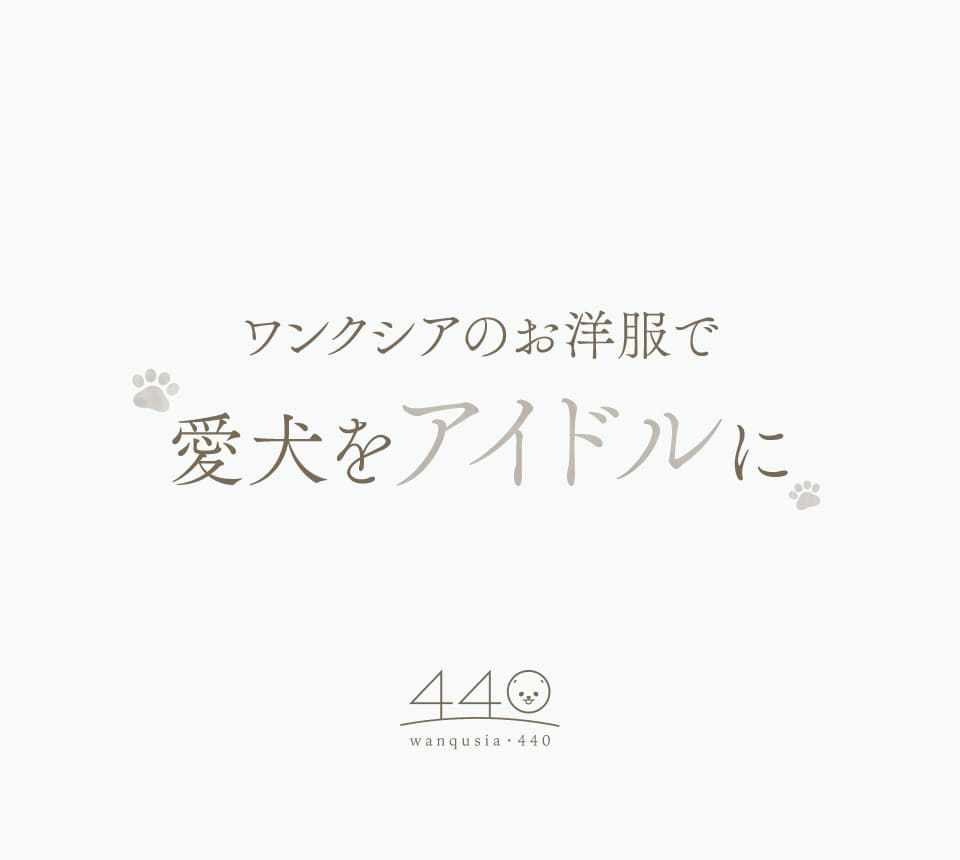ワンちゃんが脱水症状になってしまった時、どんなことに注意をしたらよいのでしょうか?
ひどい脱水状態に陥ってしまうと、命にかかわることもあります。
この記事では、ワンちゃんの脱水症状の原因や治療法について紹介しますのでご覧下さい。
犬の脱水症状の症状は?
ワンちゃんが脱水時に見られる症状は、食欲が落ちる、元気がない、嘔吐や下痢、ハァハァと呼吸が荒い、皮膚の弾力がない、おしっこが少ない、おしっこが濃いなどがあげられます。
家庭で簡単にできるワンちゃんの脱水症状を見分ける『ツルゴールテスト』という皮膚つまみ試験があるのでご紹介します。
やり方は、ワンちゃんの首や背中の皮膚を軽くつまんで離します。
皮膚を離してから元の状態に戻るまでの時間を測り、2秒以内に皮膚が戻るようでしたら正常です。
それ以上かかる場合は、脱水を疑えます。
ただ、年齢や体格、皮膚をつまむ場所によって時間が異なる場合があるので、ワンちゃんが元気な時に皮膚が戻るまでの時間を計測しておくとよいです。
犬が脱水症状になる原因は?
脱水症状は、健康維持に必要な水分が体内から過剰に失われて起こります。
ワンちゃんが脱水症状になる原因は、下痢、嘔吐、利尿剤の使用、食事や水分を十分に摂れていない事や、病気によるものなど様々です。
本来必要とする水分量が保てない状態で、下痢や嘔吐をしてしまうと、たくさんの水分を失ってしまいます。
また、脱水は水分だけでなく電解質のバランスも失うため、体に様々な不調を起こしやすくなるので注意が必要です。
脱水症状の原因になる病気がある?
脱水症状の原因になる病気は、どんな病気があるでしょうか?
原因となる病気をいくつか紹介します。
- 熱中症:体が高温になることで、体内の水分が過剰に失われます。
- 糖尿病:尿を必要以上に出してしまうので、脱水が進みます。
- 下痢や嘔吐:体内の水分が過剰に失われてしまうので、脱水につながります。
- 腎臓病:食欲が落ち、尿が多く出てしまうので脱水が起こりやすいです。
- 副腎皮質機能低下症:水分維持が必要なホルモンが低下し、尿の量が多くなってしまうので脱水になりやすいです。
その他にも胃腸炎、膵炎、腫瘍、異物摂取など、多くの疾患からワンちゃんは脱水症状を起こしてしまうことがあります。
脱水症状は夏だけでなく冬も起こる?
夏に熱中症による脱水症状は珍しくありませんが、脱水症状は冬も起こります。
真夏の熱い時期は、飼い主さんもワンちゃんが熱中症にならないように注意する事が多いので、脱水が予防されている季節とも言えます。
しかし、秋から冬の寒い時期は、ワンちゃんがあまり水分を取らないことや暖房のきいた部屋などで過ごすため、脱水を起こしてしまう場合もあるので注意が必要です。
脱水症状になったらどのように対処すればいい?
脱水症状は、適切な処置が遅れると命にかかわることがあります。
例えば、歩けない、立てない、体が熱い、体が冷たい、呼吸が荒い、痙攣、反応が遅い、反応がない
尿が少ない・出ていないなどの症状の場合は、急いで動物病院で受診をしましょう。
また、ワンちゃんが脱水症状を起こしてしまった時の応急処置は、水分を口から摂取することです。
もし、ワンちゃんが水分を口から摂取できるときは、容器から与えてましょう。
自分で飲めない場合は、スポイトのような物を使い少しずつ飲ませてあげるとよいです。
ただし、そのまま経過観察しているのは危険なので、動物病院で受診をしましょう。
脱水症状にならないように、愛犬のケアをしましょう

ワンちゃんが脱水症状にならないように予防するには、いつでも水分を摂取できる環境にしておくことが大切です。
自宅では給水容器が空にならないようにし、ワンちゃんとの外出では携帯用の給水容器を持っていきましょう。
また、寒い季節や高齢犬で自分から十分に水分を摂取しない場合は、ドライフードに水分を混ぜたりウエットフードを使うなどするとよいです。
脱水症状にならないように、ワンちゃんをケアしましょうね。